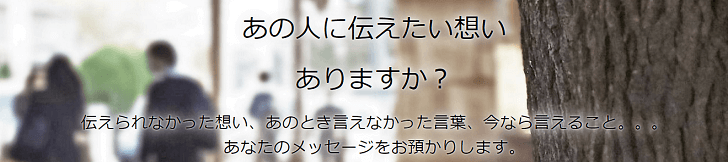三田地さんの掲示板
全国の三田地さんに関する掲示板です。三田地さんに関するエピソードや三田地さんの由来、「三田地会」、「三田地」サークルなどの存在や三田地さん限定サービスなどのお得情報等、三田地さんに関することを教えてください。足跡&一言だけでもぜひお願いします!!
このページは自分のお仕事をPRしたり、ホームページのアドレスを載せてもOKです。 ただし無関係の広告や自分の名前ではないページでのPRは削除します。
※個人を特定できる投稿はしないでください。
この掲示板は 17878名の人に閲覧されています。
投稿フォーム
|
ヤマト王権や律令政府は未開発だった東北に順次城柵を築いて建国するわけですが、目的は土地(新田)開発による戸籍制定と税金徴収、一定期間の軍事訓練及び徴兵(男子)でした。たとえば、715年に坂東の富民を陸奥に1,000戸移配した記録があります。一戸は20人単位ですから20,000人を仙台平野に強制移住させたわけです。ただし、そのような記録はほんの一部と思われます。反抗した捕虜を東北に移住させたり、方針に従わない者たちを遠国へ移住させたりしました。また、一旦筑後へ移住させた者を罰としてさらに摂津へ再配流した例もあります。それらはすべて組織的に行われました。分配や移配は記録に残っているだけでも35ヶ国となっています。 記事の訂正があります。新潟の柵造営は大化改新後すぐに実施されています。城柵設置を足がかりに阿倍比羅夫船団の大規模な威力偵察が658年に行われており、肥沃な東北全体の建郡建国を急ぎヤマト王権の兵力国力増強をより確かなものにするのが目的だと考えられます。 改新以降、647年に渟足柵(新潟市)、648年に磐舟柵(村上市)、都岐沙羅柵(一説には渟足と磐舟の中間に在ったらしいが海没しているとも云われる)の3箇所、郡山官衙のような本格的な城柵ではなかったものの越の国の体裁を整えており比羅夫の威力偵察は功をそうしています。 ヤマト王権の時代ですが、仙台平野では500年代後半には阿武隈川南岸まで国造がありました。北岸には国造は置いてなかったので足がかりとして新たに600年代中頃に郡山官衙や名生官衙を造営したわけです。ただし、数百年前から遠見塚や雷神山古墳他多数の古墳群があったように仙台平野には種々の在地豪族(祖先は毛野氏系統が中心)が根を張っていたと考えられます。その頃の倭国は唐、新羅とのせめぎ合いを抱えており658年、阿部比羅夫船団を編成し東北日本海側沿岸に対する威力偵察を始めました。現地人を懐柔して最終的には橋頭保(城柵造営)を設置するのが目的でした。 600年代初頭といいますと推古帝の御代、王権は南小泉(仙台市)の拠点集落を政治的に抑えたとの記録があったことを思い出します。南小泉は奥大道沿いの集落であり古代から遠見塚古墳を取り込んでいる地域です。南小泉は古くから人が集まり栄えていた地域であったと考えられます。国分寺や国分尼寺も言ってみれば南小泉エリアに造営されています。 前に述べたように300〜500年代が仙台市の大野田古墳群、遠見塚古墳、雷神山古墳等の時代ですが……九州、中国、関西、関東地方を中心に大陸や半島からの大量難民、移住は始まっていたと考えられます。仙台市教委では官衙発掘調査の結果、仙台平野の中央から北部においても郡山官衙造営(600年代中頃)以前の600年代初めから大規模移住が行われていたと考えています。その前からだった可能性もあります。 黄巾の乱に関わった兵や民間人は併せて30〜40万人と云われていますが、日本列島に来た難民や移民の数は500万人を優に超えるわけです。列島に渡ってきた人たちは黄巾の乱関連だけでないことは明白です。古墳時代に日本列島に流入した東アジア人は全体人口の70%、7割方を占めるわけですからまさに波状的に怒涛のように列島にやって来ています。ただし、その頃の列島は前述のごとく人口密度の極端に低い島であり、道もろくにない原生林や河川湖沼あるいは原野の方が格段に多かったと思われます。 後漢の末期184年に黄巾の乱(組織的な農民が主力であった)が起きました。結果は後漢の勝利でしたが、これを契機に後漢は衰退の一途を辿りついに滅亡してしまい、世の中は魏呉蜀の三国時代に移っていきます。ですが、この群雄割拠も終わりをつげます。この後漢や三国時代の滅亡の影響で日本の古墳時代の人口が爆発的に増えていきました。 これはネット記事からの抜粋ですが、縄文中期である4000年〜5000年前の人口密度は関東地方が最も多く300人/100km²、東日本全体としては100人 /100km²、西日本はわずか20人/100km²しかいませんでした。縄文時代は東日本の方が暮らしやすかったようです。ちなみに、100km²とは10km✕10kmの範囲で例えば猪苗代湖くらいの大きさです。山手線の内側の約1.6倍の広さという事になりましょうか。 弥生時代までに列島に流入してきた人たちは主にツングース系であり満族や女真族の後裔が多かったのです。弥生時代までは100万人にも満たなかった列島の人口は、古墳時代に入ると急激に増えて540万人の人口になりました。なんと弥生時代の9倍の人口になります。これは中国の黄河流域を中心とした漢民族の移民がほとんどと云われています。日本の古墳時代は後漢の後半期であり戦乱に明け暮れた時代でした。言ってみれば大陸から渡ってきた大量難民というわけですが、多種多様の技術を持ち合わせており在地人である倭族と交流して列島に自然に溶け込み根付いていったと思われます。これが私どもの祖先のルーツです。 大化改新以降、律令国家は宮城を始めとして東北全体に数多くの官衙を割と短期間に集中し造営してきました。前述のごとく相当数の人員と技術者が動員されたわけですが、この事に関する新たな記事を見つけました。ここ数年のあいだに、ヒトの遺伝子などについての解析が急速に進み日本人のルーツがさらに具体的に判ってきました。端的に説明しますと、弥生時代の列島の人口は約60万人でしたが、古墳時代になり圧倒的に急激に増えています。その数は弥生時代の9倍の540万人です。縄文時代は最大で27万人と云われています。奈良時代の700年代中頃は600〜700万人と予想されています。 |
次の10件 >>