体の部位がつく名字
概要
体の一部である、頭や口、足や手、さらには脇や腰、肩などを名字の一部として使っているのは意識してみると意外と多いものです。
一部を紹介すると
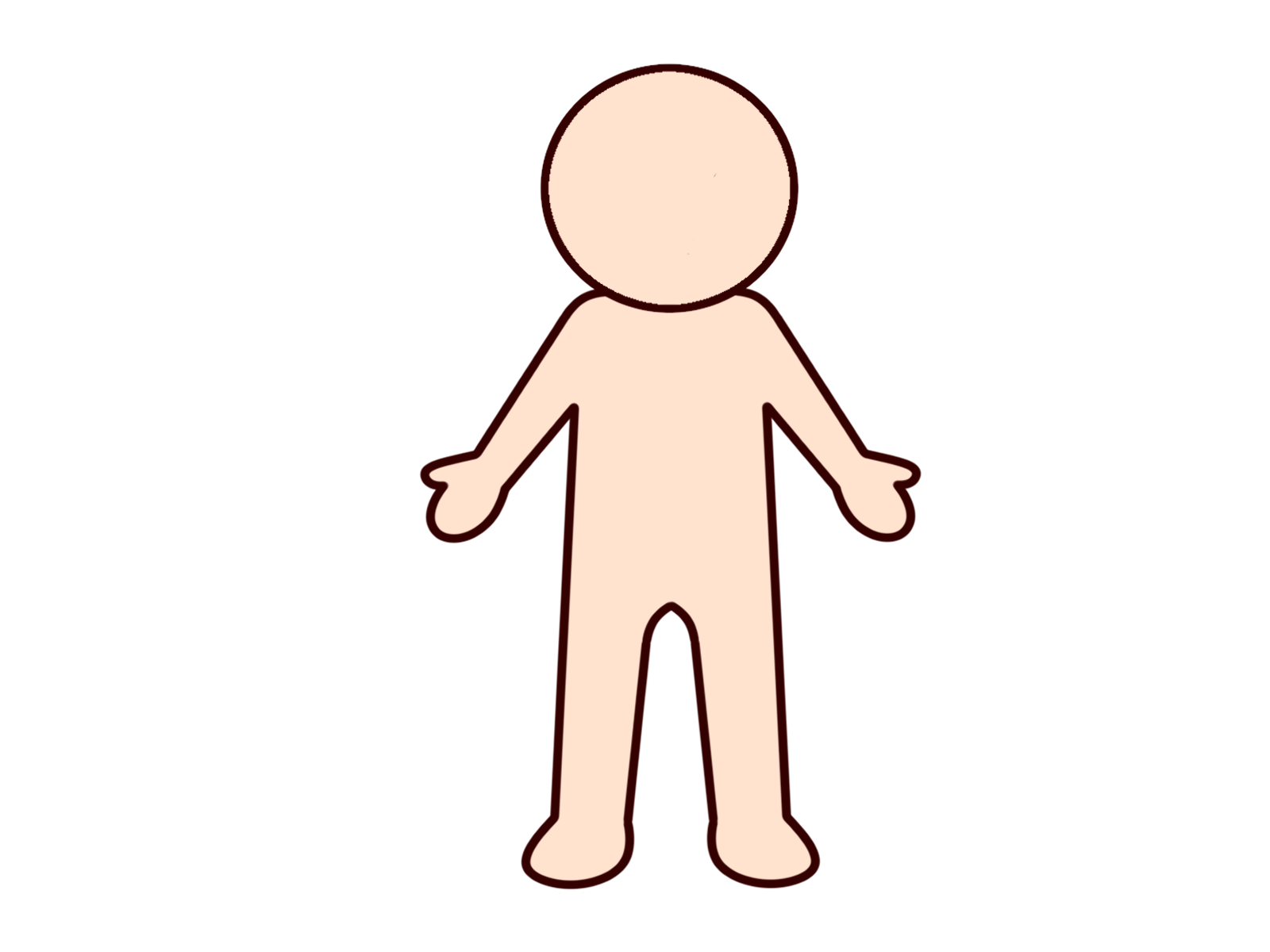 子供の頃はその名字から、あだ名にされてあまり良い思い出になっていない人もいるかもしれません。
このページではそんな体の部位がどんな経緯で名前についたのか見ていきましょう。
子供の頃はその名字から、あだ名にされてあまり良い思い出になっていない人もいるかもしれません。
このページではそんな体の部位がどんな経緯で名前についたのか見ていきましょう。
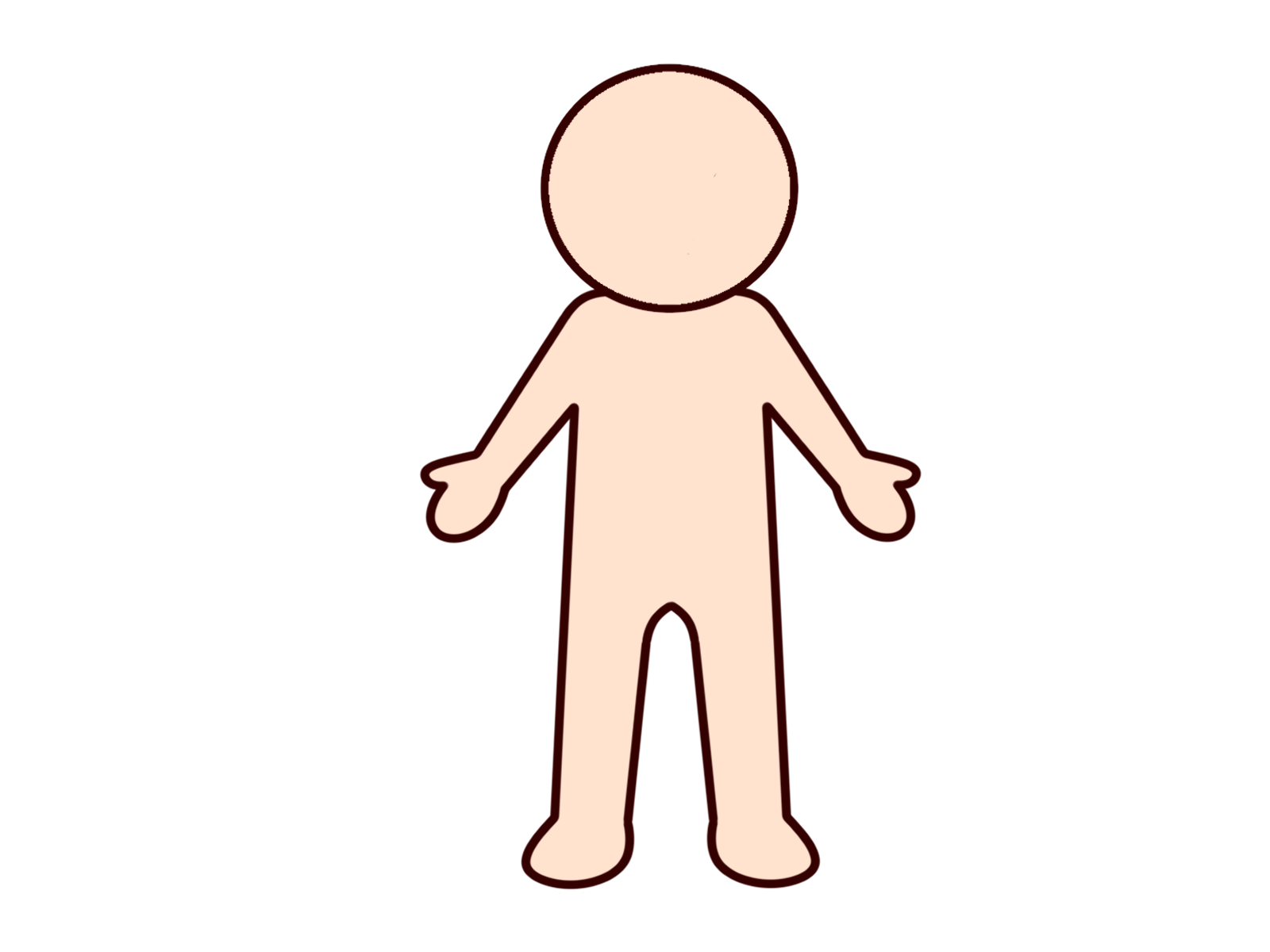 子供の頃はその名字から、あだ名にされてあまり良い思い出になっていない人もいるかもしれません。
このページではそんな体の部位がどんな経緯で名前についたのか見ていきましょう。
子供の頃はその名字から、あだ名にされてあまり良い思い出になっていない人もいるかもしれません。
このページではそんな体の部位がどんな経緯で名前についたのか見ていきましょう。
体の部位を冠する珍しい苗字
 爪さんは、庄屋をやっていた。近くの川が氾濫するたびに、爪家と近くの庄屋が川の橋を架けた。そのため領主より、橋の重要部分である、橋と爪(橋の両端で地面に食い込む部分のこと)という言葉を名字として賜り、両家が互いに名乗った。
髭さんは、由来はもちろんご先祖様が立派な髭を蓄えていたから。。。かと思いきやそうとも限らないようです。
その他にも、靨(えくぼ)さんや、臍島(ほそじま)さん、白髪(しらが)さん、臂さん、指さん、耳さんなどといった珍しいものもあるようです。
爪さんは、庄屋をやっていた。近くの川が氾濫するたびに、爪家と近くの庄屋が川の橋を架けた。そのため領主より、橋の重要部分である、橋と爪(橋の両端で地面に食い込む部分のこと)という言葉を名字として賜り、両家が互いに名乗った。
髭さんは、由来はもちろんご先祖様が立派な髭を蓄えていたから。。。かと思いきやそうとも限らないようです。
その他にも、靨(えくぼ)さんや、臍島(ほそじま)さん、白髪(しらが)さん、臂さん、指さん、耳さんなどといった珍しいものもあるようです。
体の部位を名字にした理由
 体名字の多くは地形、地名が由来となっています。
ただ現代人が直感的にイメージするところとは少し違う点もあるようなのでいくつか例を挙げてみていきましょう。
体名字の多くは地形、地名が由来となっています。
ただ現代人が直感的にイメージするところとは少し違う点もあるようなのでいくつか例を挙げてみていきましょう。
森口は森の入り口というより、例えば、その土地の盛り上がったところ、一段高いところに神様をまつった神社や寺などを作りました。その盛り上がった地形を「盛り」といい、そこにある神社や寺などへ続く道を、神への入り口を人の口に見立て「盛りの入り口」転じて「森口」と呼んだ。
川口は川の入り口というより、川の支流が本流に合流する場所のことを言います。ちなみに現在の埼玉県川口市を上空から眺めると、支流の新芝川が本流の荒川と交わる地域になっており、まさにそのような地形になっています。
川股は川が人の股のように分かれる場所を言います。川尻は川の下流、海が合流する地点を言いますが、これは田んぼで使った水を最終的に海に排泄する地点、また水上交通の終点という意味で尻の字が使われています。
川のように水に関するものには、口や尻が使われる苗字はいくつかあり、田(田口、田尻)、沢(沢口、沢尻)、江(江口、江尻)などがあります。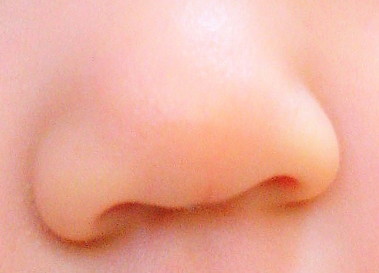
他にも海や湖などに突き出した岬のような地形を「鼻」と呼ばれ、名字に使われた。岬さば(はなさば)なんてお魚もいます。瀬戸内海にはこのように岬に鼻とついている地名が見られます。
そしてこの鼻の字はより縁起のよい「花」の字を付けます。
脇田は大切なものの傍という意味で使われることが多く、神社やお寺、大名屋敷などのすぐそばを「脇田」と呼んだそうです。もちろん田んぼの脇を脇田と呼ぶこともあります。
また脇には泉が湧くという意味もあり、天然の湧き水を初めて引っ張り最初に田んぼを耕した人の事を脇田と言ったりもしたようです。
足立の「あ」は「兄」などのように目上、また高いところという意味があり、かつ日本には高いところに神が宿るという信仰があるため、森口の例で示したように盛り上がったところを指します。その盛り上がったところに住んだ人が足立さんと呼ばれたようです。
足立には植物の葦が生える湿地帯、葦が立つところの事を足立と呼んだという説もある。
このように自然への人格化によって地形に人間が投影され、そのことで人の部位が地名として付けられ、さらにその地名が人名に戻ってくるという循環を見ることが出来ます。
名字には先祖が暮らした墓所の「風景」が込められているということですね。
地形以外の由来となる苗字
目(さっか)さんの由来
 目と書いて「さっか」と読む名字がある。埼玉ブロンコス所属のバスケットボール選手で目健人(さっかけんと)さんが有名です。
ルーツは山口県宇部市で、その由来は宇部市の資料によると「目は国司時代の小典即ち四等官官の官職名なり」とあり、律令時代の大目という官職が由来となります。
もともとは大目「そうかん」とよばれ、それが「さかん」→「さっか」と呼ばれるようになったもので、公文書の作成、行政事務、文書管理等を行う仕事。
すべてのに目を通す人、目を配る人という意味から「目」の字があてられたようです。
目と書いて「さっか」と読む名字がある。埼玉ブロンコス所属のバスケットボール選手で目健人(さっかけんと)さんが有名です。
ルーツは山口県宇部市で、その由来は宇部市の資料によると「目は国司時代の小典即ち四等官官の官職名なり」とあり、律令時代の大目という官職が由来となります。
もともとは大目「そうかん」とよばれ、それが「さかん」→「さっか」と呼ばれるようになったもので、公文書の作成、行政事務、文書管理等を行う仕事。
すべてのに目を通す人、目を配る人という意味から「目」の字があてられたようです。
舌(ぜつ)さんの由来
 貴船神社、牛鬼という神様をまつった牛一社(ぎゅういちしゃ)があり、この牛鬼が舌という名字の由来と言われています。
貴船大明神が天から降りてきたときに鬼を伴ってきた。この鬼に神々の世界の事をしゃべってはいけないと言っていたのに、鬼はしゃべってしまった。そのため大明神は鬼の舌を八つ裂きにしまったという伝説がある。
その後人間になった、この牛鬼の子孫がこの戒めを忘れないように舌という名字にした用です。舌家の家紋も八の字で下を八つ裂きされたこの教訓をあらわします。
この由来は「舌はうまく使えば人々をつなぎ幸せにするが、使い方を誤ると人を傷つけてしまう」という教訓を伝えています。
貴船神社、牛鬼という神様をまつった牛一社(ぎゅういちしゃ)があり、この牛鬼が舌という名字の由来と言われています。
貴船大明神が天から降りてきたときに鬼を伴ってきた。この鬼に神々の世界の事をしゃべってはいけないと言っていたのに、鬼はしゃべってしまった。そのため大明神は鬼の舌を八つ裂きにしまったという伝説がある。
その後人間になった、この牛鬼の子孫がこの戒めを忘れないように舌という名字にした用です。舌家の家紋も八の字で下を八つ裂きされたこの教訓をあらわします。
この由来は「舌はうまく使えば人々をつなぎ幸せにするが、使い方を誤ると人を傷つけてしまう」という教訓を伝えています。
※この記事はNHK2017/12/7放送の人名探求バラエティー 日本人のおなまえっ!を参考に追加取材して作成されています。
© 2013-.
sijisuru.com All rights reserved.