法花津姓に関する由来・ルーツのページです。"法花津"がつく地名、同姓の多い地域、使われている字の意味、成り立ちや出自といった様々な観点でルーツを検証しています。またユーザ様よりよせられたこの苗字の由来、逸話等を掲載しております。掲載されていないルーツや逸話をご存知の方は教えていただけると助かります。
法花津姓の名字の由来と起源に関する投稿
Delete Task
削除用Passwordを入力してください
文字の意味から由来を探る
‘法’の由来
| 種類: | 会意文字 |
|---|
| 意味: | のり。きまり。のっとる。手本にする。フラン(通貨の単位)。 |
|---|
| 由来: | もと「水+しかと馬に似た珍しい獣の姿+去(ひっこめる)」で、池の中の島に珍獣をおしこめて、外に出られないようにしたさま。珍獣はそのわくの中では自由だが、そのわく外には出られない。ひろくそのような、生活にはめられたわくをいう。 |
|---|
‘花’の由来
| 種類: | 会意兼形声文字 |
|---|
| 意味: | 植物の「花」。植物を表す「艹(くさかんむり)」と「変化する」という意味をもつ「化」を加えてできたのが「花」。はな。 |
|---|
| 由来: | 化カは、たった人がすわった姿に変化したことをあらわす会意文字。花は「艸(植物)+音符化」で、つぼみが開き、咲いて散るというように、姿をいちじるしくかえる植物の部分。華(中心のくぼんだまるいはな)とはもと別字であったが、のち混用された。 |
|---|
‘津’の由来
| 種類: | 会意兼形声文字 |
|---|
| 意味: | つ。渡し場。船着場。 |
|---|
| 由来: | 津の字の右側はもと「聿(手で火ばしを持つさま)+火(もえかす)」の会意文字で、小さい燃えかす。または、「聿(手でふでを持っているようす)+彡(しずくがたれるしるし)」の会意文字で、わずかなしずく。津はそれにさんずいを加えたもので、水が少なく、尽きようとしてたれることを示す。のち、うるおす、しめった浅瀬などの意を派生した。 |
|---|
氏神の由来を探す
苗字にはその地域で称えられていたものに由来するケースもあります。ここでは"法花津"の名がつく神社を紹介しています。
© 2013-.
sijisuru.com All rights reserved.

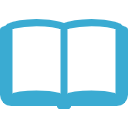 法花津姓のページ
法花津姓のページ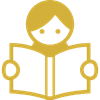 法花津の読み方
法花津の読み方 法花津姓の人口
法花津姓の人口 法花津姓の特徴
法花津姓の特徴 法花津姓のイメージ
法花津姓のイメージ 法花津姓交流掲示板
法花津姓交流掲示板 相性のいい女子の名前
相性のいい女子の名前 相性のいい男子の名前
相性のいい男子の名前 法花津姓の有名人
法花津姓の有名人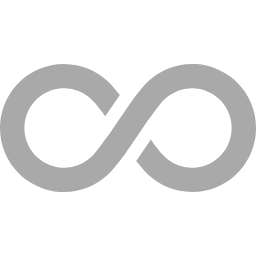 ダジャレを作る
ダジャレを作る