全国分布検索 > 本告姓都道府県世帯数
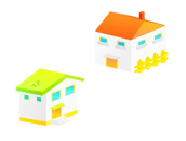
本告姓の人口
※あくまで参考値であり保証するものではありません。
全国の推定人口
データ無し
推定人口の順位
不明
本告さんは特定の地域に住まわれている方が多いかもしれませんがとても珍しい苗字です。珍しいがゆえに初対面の人には必ず「珍しい苗字ですね」などと言われてちょっと辟易している人もいるかもしれません。
※本サイトではプライバシー保護のため人口が少ない場合は[0~10前後]、[ほとんどいない]等と表現し、端数についてはも四捨五入させているため[全国の推定人口]と各都道府県の[人口]の合計は一致しません。
本告姓 ランキング上位
 佐賀県(約260人)
佐賀県(約260人)
 大阪府(約70人)
大阪府(約70人)
 埼玉県(約60人)
埼玉県(約60人)
 福岡県(約60人)
福岡県(約60人)
 神奈川県(約50人)
神奈川県(約50人)
本告姓 県内比率ランキング上位
 佐賀県(約0人)
佐賀県(約0人)
 埼玉県(約0人)
埼玉県(約0人)
 神奈川県(約0人)
神奈川県(約0人)
 愛知県(約0人)
愛知県(約0人)
 大阪府(約0人)
大阪府(約0人)
本告姓都道府県分布一覧
| 都道府県 | 人口 | 県内比率 |
|---|---|---|
| 0~10前後 | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| 約60 | 0.00% | |
| 約20 | 0.00% |
| 都道府県 | 人口 | 県内比率 |
|---|---|---|
| 約40 | 0.00% | |
| 約50 | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| 約50 | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% |
| 都道府県 | 人口 | 県内比率 |
|---|---|---|
| ほとんどいない | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| 約70 | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% |
| 都道府県 | 人口 | 県内比率 |
|---|---|---|
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| 約60 | 0.00% | |
| 約260 | 0.03% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% |
本告姓の地域分布
本告姓の都道府県分布
本告という名字は全国で11339番目に多い苗字となっています。おおむね100万人に4.8人くらい居ます。佐賀県や大阪府や埼玉県や福岡県や神奈川県や愛知県にいらっしゃるようです。また県内の人口比率だと佐賀県や埼玉県や神奈川県や愛知県や大阪府や福岡県にに多くいらっしゃるようです。地域としては九州地方に多い名前のようです。もしかすると地名に本告さんの名前がついているところがあるかもしれません。調べてみると苗字の意外なことがわかるかもしれませんね。そして佐賀県や東京都や千葉県に移り住まわれた方が多いようです。
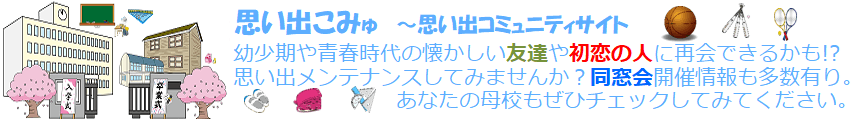
本告さんの由来
- 肥前国の櫛田宮は旧長崎街道神埼宿のほぼ真ん中に所在し、博多の櫛田神社の本家として知られている。その創建は、社伝によれば景行天皇が神埼地方を巡行された折、この地に不幸が続いて人民が苦しんでいた。そこで、神を祭りあがめたら災厄がなくなった。そして、櫛田宮の創建はこの時であるという。さらに、神の幸をうける地というところから「神幸(かむさき)の里」と名付けられ、今は「神埼」と書かれるようになったのである。 永久三年(1115)、鳥羽天皇が櫛田宮を修造され、伴兼直と本告道景を勅使別当職として下向させられた。そして、伴兼直は執行家の祖となり、本告道景が本告家の祖になったのだという。ちなみに、本告は「もとおり」と読み、牟田ケ里七百町を本領とした。
- 『もとおり』が訛り『もとい』というようになった。 戦国時代の天文二十二年(1553)十月、龍造寺隆信が蓮池城を攻めたとき、本告牟田城主の本告頼景は三百余騎の兵を率いて、蓮池城攻めに加わったが、蓮池方の馬場越後守に討たれて戦死した。永禄元年(1558)には、蓮池の小田政光を先陣として、本告義景がこれに従って出兵している。小田勢は神埼口の大手門から勢福寺城に入り、長者林を舞台にした莞牟田縄手で、神代勝利と戦い戦死した。このとき、一方の社家である執行氏は神代方にあった。 龍造寺の勢力拡大を懸念した大友宗麟は、先に滅亡した少弐氏の再興を画策し、少弐氏を隆信の対抗勢力にしようとしたことで、大友・龍造寺両氏の緊張は一気に高まった。元亀元年(1570)、宗麟は隆信を討つ好機と判断し、三万の軍勢を肥前に差し向けた。またたくく間に大友氏は龍造寺氏居城佐嘉城を包囲した。この窮地に際して龍造寺氏の重臣鍋島直茂は乾坤一擲の奇襲作戦を行い、龍造寺軍は奇跡的勝利を得たのであった。 この「今山の合戦」ののち、本告増景は龍造寺氏にいち早く和平を申込み許された。以後、本告氏は龍造寺氏の配下に属し、元亀三年には、龍造寺隆信が東肥前を制圧したとき、櫛田宮に陣を布いたことが知られる。龍造寺隆信・政家の幕下衆知行を見ると、神埼郡本告・三百町本告左馬大夫がみえている。この左馬大夫は本告義景の嫡子信景であった。
【名字由来教えてください】
本告姓の由来やルーツ、一族の伝承や秘話等についてご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
他の苗字の全国の分布を調べる
同じ名字の人と交流する
同じ名字の人が集うページを設置しております。同姓の方と交流してみてください。本告姓についてもっと詳しく
© 2013-.
sijisuru.com All rights reserved.
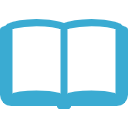 本告姓のページ
本告姓のページ 本告の由来
本告の由来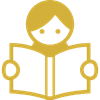 本告の読み方
本告の読み方 本告姓の特徴
本告姓の特徴 本告姓のイメージ
本告姓のイメージ 本告姓交流掲示板
本告姓交流掲示板 相性のいい女子の名前
相性のいい女子の名前 相性のいい男子の名前
相性のいい男子の名前 本告姓の有名人
本告姓の有名人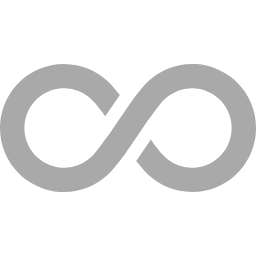 ダジャレを作る
ダジャレを作る