十二所 姓の由来

十二所姓の由来のページです。"十二所"を冠する発祥の地や同姓の多い地域、使われている漢字、成り立ちや出自といった様々な観点で由来や起源を検証しています。また皆様よりよせられた姓のルーツや逸話等を掲載しております。未掲載の由来や逸話をご存知の方はぜひ情報提供をお願いいたします。
十二所姓の名字の由来と起源に関する投稿
文字の意味から由来を探る
‘十’の由来
| 種類: | 指事文字 |
|---|---|
| 意味: | とお。と。 |
| 由来: | 全部を一本に集めて一単位とすることを|印で示すもの。その中央がまるくふくれ、のち十の字体となった。多くのものを寄せ集めてまとめる意を含む。促音の語尾pがtに転じた場合はジツまたはジュツと読み、mに転じた場合はシン(シム)と読む。証文や契約書では改竄カイザンや誤解をさけるため、拾と書くことがある。 |
‘二’の由来
| 種類: | 指事文字 |
|---|---|
| 意味: | ふた。ふたつ。 |
| 由来: | 二本の横線を並べたさまを示すもので、二つの意を示す。弍・貳(=弐)は、古文の字体で、おもに証文や、公文書で改竄カイザン・誤解を防ぐために用いる。 |
‘所’の由来
| 種類: | 形声文字 |
|---|---|
| 意味: | ところ。場所。 |
| 由来: | 「斤(おの)+音符戸」で、もと「伐木所所=木ヲ伐ルコト所所タリ」〔詩経〕のように、木をさくさくと切り分けること。その音を借りて指示代名詞に用い、「所+動詞」の形で、…するその対称をさし示すようになった。「所欲」とは、欲するその物、「所至」とは、至るその目標地をさし示したいい方。後者の用法から、さらに場所の意を派生した。 |
地名から由来を探る
地名ルーツの名字は多いため地名に名字が含まれるものを見てみましょう。「十二所」を含む地名を都道府県ごとに表示しています。
| 神奈川県 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
鎌倉市十二所 (かまくらしじゅうにそ)
| ||||||
| 兵庫県 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
姫路市十二所前町 (ひめじしじゅうにしょまえちょう)
| ||||||
|
|
養父市十二所 (やぶしじゅうにしょ)
| ||||||
| 秋田県 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島県 | |
|---|---|
|
|
会津若松市北会津町十二所 (あいづわかまつしきたあいづまちじゅうにしょ)
|
住んでいる地域から由来を探る
本サイトのデータでは十二所姓の方は全国に殆どいらっしゃらないようす。 最も多く住んでいらっしゃる都道府県は福島県のようです。都道府県別在住数1位の福島県には北会津町十二所、都道府県別在住数が2番目に多い神奈川県には十二所などの地名があるようです。| 順位 | 都道府県 | 世帯数 |
|---|---|---|
| 福島県 | 約30人 | |
| 神奈川県 | 0~10前後 |
十二所姓の成り立ち
| 地名 | 地形 | 職業 | 事物 | 拝領 | 明治 | 派生 | 外来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 |
十二所姓の出自
| 武家 | 公家 | 庶民 | 職人 | 神主 |
|---|---|---|---|---|
| 〇 |
十二所姓の起源
| アイヌ | 蝦夷 | 琉球 | 台湾 | 中国 | 朝鮮 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
氏神の由来を探す
苗字にはその地域で称えられていたものに由来するケースもあります。ここでは"十二所"の名がつく神社を紹介しています。十二所神社(じゅうにしょじんじゃ)
茨城県常陸大宮市北富田968番
十二所神社(じゅうにしょじんじゃ)
愛知県一宮市光明寺字大条戸39番
十二所神社(じゅうにしょじんじゃ)
栃木県小山市立木122番
十二所神社(じゅうにしょじんじゃ)
福島県耶麻郡磐梯町大字大谷字中落合4814番
十二所神社(じゅうにしょじんじゃ)
徳島県海部郡海陽町浅川字大山8番
十二所神社(じゅうにしょじんじゃ)
高知県香美市物部町小浜310番
十二所神社(じゅうにしょじんじゃ)
茨城県常陸大宮市小玉552番
十二所神社(じゅうにしょじんじゃ)
栃木県那須烏山市横枕417番
十二所神社(じゅうにしょじんじゃ)
高知県長岡郡大豊町中村大王1184番
十二所神社(じゅうにしょじんじゃ)
福島県大沼郡会津美里町宮木字早泥21番3
十二所姓についてもっと詳しく
© 2013-.
sijisuru.com All rights reserved.
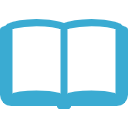 十二所姓のページ
十二所姓のページ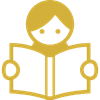 十二所の読み方
十二所の読み方 十二所姓の人口
十二所姓の人口 十二所姓の特徴
十二所姓の特徴 十二所姓のイメージ
十二所姓のイメージ 十二所姓交流掲示板
十二所姓交流掲示板 相性のいい女子の名前
相性のいい女子の名前 相性のいい男子の名前
相性のいい男子の名前 十二所姓の有名人
十二所姓の有名人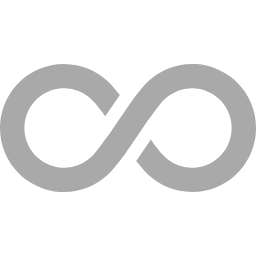 ダジャレを作る
ダジャレを作る