印南 姓の由来

印南姓に関する由来・ルーツのページです。"印南"がつく地名、同姓の多い地域、使われている字の意味、成り立ちや出自といった様々な観点でルーツを検証しています。また皆様よりよせられた苗字のルーツや逸話等を掲載しております。掲載されていないルーツや逸話をご存知の方は教えていただけると助かります。
印南姓の名字の由来と起源に関する投稿
文字の意味から由来を探る
‘印’の由来
| 種類: | 会意文字 |
|---|---|
| 意味: | しるし。しるす。はん。はんこ。はんを押す。 |
| 由来: | 左は手、右はひざまずいた人。手で押さえて人をひざまずかせることをあらわすもので、押さえつける意を含む。抑の原字。のち、上から押さえて印を押す意となった。軋アツ(押さえる)はその入声ニッショウ(つまり音)に当たる。 |
‘南’の由来
| 種類: | 会意兼形声文字 |
|---|---|
| 意味: | みなみ。 |
| 由来: | 原字は、納屋ふうの小屋を描いた象形文字。南の中の形は、入の逆形が二線にさしこんださまで、入れこむ意を含む。それが音符となり、屮(くさのめ)とかこいのしるしを加えたのが南の字。草木を囲いで囲って、暖かい小屋の中に入れこみ、促成栽培をするさまを示し、囲まれて暖かい意。転じて、暖気を取りこむ南がわを意味する。北中国の家は北に背を向け、南に面するのが原則。 |
地名から由来を探る
地名ルーツの名字は多いため地名に名字が含まれるものを見てみましょう。「印南」を含む地名を都道府県ごとに表示しています。
| 千葉県 | |
|---|---|
|
|
佐倉市印南 (さくらしいんなん)
|
| 兵庫県 | |
|---|---|
|
|
加西市小印南町 (かさいしこいなみちょう)
|
|
|
加古郡稲美町印南 (かこぐんいなみちょういんなみ)
|
| 和歌山県 | |
|---|---|
|
|
日高郡印南町 (ひだかぐんいなみちょう) |
|
|
日高郡印南町印南 (ひだかぐんいなみちょういなみ)
|
|
|
日高郡印南町印南原 (ひだかぐんいなみちょういなんばら)
|
| 福島県 | |
|---|---|
|
|
大沼郡会津美里町惣印南 (おおぬまぐんあいづみさとまちそういんみなみ)
|
住んでいる地域から由来を探る
本サイトのデータでは印南姓の方は全国に殆どいらっしゃらないようす。 最も多く住んでいらっしゃる都道府県は栃木県のようです。その後東京都、千葉県にいらっしゃる方が多くなっているようです。最も多い栃木県と2番目の東京都の差は倍以上あるため、もしかすると栃木県がこの苗字発祥の地といえるかもしれません。印南姓の方は3位までの都道府県における地名には見られないことから、地名が由来というわけではないと思われます。| 順位 | 都道府県 | 世帯数 |
|---|---|---|
| 栃木県 | 約1900人 | |
| 東京都 | 約680人 | |
| 千葉県 | 約380人 | |
| 埼玉県 | 約350人 | |
| 神奈川県 | 約310人 | |
| 愛媛県 | 約190人 | |
| 三重県 | 約130人 | |
| 大阪府 | 約90人 | |
| 福島県 | 約80人 | |
| 茨城県 | 約70人 |
印南姓の成り立ち
| 地名 | 地形 | 職業 | 事物 | 拝領 | 明治 | 派生 | 外来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 |
印南姓の出自
| 武家 | 公家 | 庶民 | 職人 | 神主 |
|---|---|---|---|---|
| 〇 |
印南姓の起源
| アイヌ | 蝦夷 | 琉球 | 台湾 | 中国 | 朝鮮 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
氏神の由来を探す
苗字にはその地域で称えられていたものに由来するケースもあります。ここでは"印南"の名がつく神社を紹介しています。印南八幡神社
和歌山県日高郡印南町印南2657番
印南姓についてもっと詳しく
© 2013-.
sijisuru.com All rights reserved.
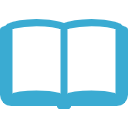 印南姓のページ
印南姓のページ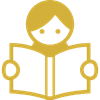 印南の読み方
印南の読み方 印南姓の人口
印南姓の人口 印南姓の特徴
印南姓の特徴 印南姓のイメージ
印南姓のイメージ 印南姓交流掲示板
印南姓交流掲示板 相性のいい女子の名前
相性のいい女子の名前 相性のいい男子の名前
相性のいい男子の名前 印南姓の有名人
印南姓の有名人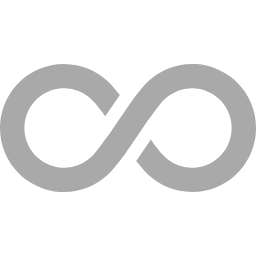 ダジャレを作る
ダジャレを作る