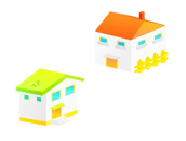
三田地姓の人口
※あくまで参考値であり保証するものではありません。
全国の推定人口
データ無し
推定人口の順位
不明
三田地さんは1000人に満たない少ない名字です。1000人に満たない少ない名字という理由だけで話題ができるため、話のきっかけがつかみやすく他人と打ち解けやすいというメリットもあるのかもしれません。
※本サイトではプライバシー保護のため人口が少ない場合は[0~10前後]、[ほとんどいない]等と表現し、端数についてはも四捨五入させているため[全国の推定人口]と各都道府県の[人口]の合計は一致しません。
三田地姓 ランキング上位
 岩手県(約380人)
岩手県(約380人)
 北海道(約90人)
北海道(約90人)
 埼玉県(約60人)
埼玉県(約60人)
 神奈川県(約50人)
神奈川県(約50人)
 千葉県(約40人)
千葉県(約40人)
三田地姓 県内比率ランキング上位
 岩手県(約0人)
岩手県(約0人)
 北海道(約0人)
北海道(約0人)
 埼玉県(約0人)
埼玉県(約0人)
 千葉県(約0人)
千葉県(約0人)
 三重県(約0人)
三重県(約0人)
三田地姓都道府県分布一覧
| 都道府県 | 人口 | 県内比率 |
|---|---|---|
| 約90 | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| 約380 | 0.03% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| 約60 | 0.00% | |
| 約40 | 0.00% |
| 都道府県 | 人口 | 県内比率 |
|---|---|---|
| 0~10前後 | 0.00% | |
| 約50 | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| 約20 | 0.00% |
| 都道府県 | 人口 | 県内比率 |
|---|---|---|
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% |
| 都道府県 | 人口 | 県内比率 |
|---|---|---|
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% |
三田地姓の地域分布
三田地姓の都道府県分布
三田地という名字は全国で11201番目に多い苗字のようです。大体100万人に4.8人くらい居ます。岩手県や北海道や埼玉県や神奈川県や千葉県や三重県に比較的多くいらっしゃるようです。また県内の人口比率だと岩手県や北海道や埼玉県や千葉県や三重県や青森県に比較的多くいらっしゃるようです。地域としては東北地方に多い名前のようです。ひょっとすると三田地という名字の高名な方がいらっしゃったのかもしれません。そして岩手県や宮城県や東京都に移り住まわれた方が多いようです。
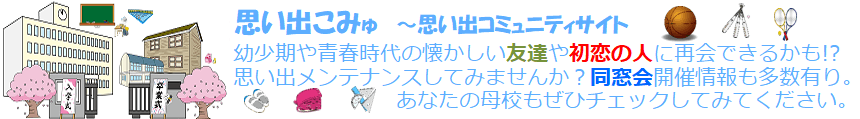
三田地さんの由来
- 藩政時代を通じて仙台にも小保町があった。若林の染師町東裏に遊女町として 存在していた。その後、広瀬川の船着場町 (今の舟丁付近)にその遊女町を移した。 この小保町の由来については今の処 明らかにされていない。 寛永14年、1637年の事である。
- そもそも太白山の名は伊達藩の漢学者が付けたと言われる。古い山の名前は倭奴ガ森 、生出ガ森である。今でも太白山のふもとに生出森八幡神社が鎮座し山頂には貴船神社の祠がある。西多賀や大野田を流れる一級河川 笊川はこの太白山が源流となっており名取川にそそいでいる。
- 甲斐の武田家重臣に飯富おぶ兵部がいた。 これもオボにつながる。仙台の秋保地区に 飯富山の山号をもつお寺がある。イイトミなのかオボと呼んでいるのかここではわからないが実体は明らかにオボである。太白山は昔は生出ガ森ウドガモリと呼ばれたらしいが、もとは倭奴ガ森イドガモリであろう。茂庭地区も生出オイデと言っているが、これもウド、イドが原型である。
- 宮城県登米に保呂羽館があり秋田県の横手にも保呂羽山がある。宮城県の沢乙や八乙女の地名も少し気になる処である。保呂羽系地名は探せばもっとあるかも知れない。
- 屋号の上宝呂林を名乗る三田地家はその昔宝呂林という地区から来住したのかも知れない。また、屋号の上下は河川の上下の意味がある。岩手県北によくみられる地名の乙茂、小友、小本、重茂はオモヒ、オボ、オロー、 ユーロであり、於保や思い、オモニ、オルチに通じる気がする。
- 保呂羽山や保呂、オロ、ユーロ、岩泉の袰綿地区、三田地家の屋号上宝呂林などすべて保呂羽(オロチ、オルチ…)信仰に通じるものです。後代に様々な漢字が当てられています。
- 中国の少数民族は現在55あるとされが、実際にはもっと細かく分けられるという。 一方ロシアでは大まかには30〜40あり、細かく分ければ190の少数民族がいるという。はるか大昔に中国とロシアの少数民族すべてが日本列島に移住したとは思えないが、列島に渡ってきた各民族が出身地の神々を祀ったことが八百万の神々につなが ったのかと連想させる。
- [條ウル神古墳]の所在地は奈良県御所市。巨石を積み重ねて用いた石室は他を圧倒する。奈良盆地の古代有力氏族巨勢氏の 首長クラスの墳墓であり、大きさは 石舞台古墳とほぼ同等である。
- 氏家ウチエ、うるち、オロチ、伊治いじ委奴いど、アイヌ、上野、いじ、イヌはみな共通である。東北地方の保呂羽信仰は ウルチ信仰に通じる。畿内に条ウル古墳が あり、これもウルチとの関連があり そうだ。岩泉の宇霊羅山も実はオロチと読める。宇霊羅うれいら(ウーロー)山信仰も北東北の保呂羽ホロハ信仰につながる。袰綿も保呂羽オロハであり語源はオロチである。オロチ大蛇信仰はおそらくアムール河(水神)の事を指している。日本人の祖先であるツングー系民族はアムール川下流域に住んでいた。それが ニブヒ族、ウルチ族、ナナイ族である。
- 比叡の叡の文字は、天子や英知、かしこいの意味を持つ。日吉ひよしは、ひき、ひじ ひるき、ひえとも読む。比地ひじ、比治、 伊治いじ、氏家うじえ、壱岐いき、五木 いき、いつき、居木いるき、おるき、五木、井城いきなど後から漢字をあてただけで語源は同じである。特に居木や氏家が分かりやすいかも知れない。ウルチ米や山菜のウルイの 名称も関係性があるかもだ。
【名字由来教えてください】
三田地姓の由来やルーツ、一族の伝承や秘話等についてご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
他の苗字の全国の分布を調べる
同じ名字の人と交流する
同じ名字の人が集うページを設置しております。同姓の方と交流してみてください。三田地姓についてもっと詳しく
© 2013-.
sijisuru.com All rights reserved.
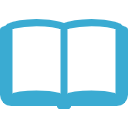 三田地姓のページ
三田地姓のページ 三田地の由来
三田地の由来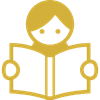 三田地の読み方
三田地の読み方 三田地姓の人口
三田地姓の人口 三田地姓の特徴
三田地姓の特徴 三田地姓のイメージ
三田地姓のイメージ 三田地姓交流掲示板
三田地姓交流掲示板 相性のいい女子の名前
相性のいい女子の名前 相性のいい男子の名前
相性のいい男子の名前 三田地姓の有名人
三田地姓の有名人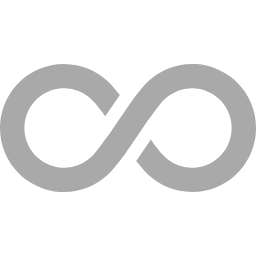 ダジャレを作る
ダジャレを作る