
安姓の人口
※あくまで参考値であり保証するものではありません。
全国の推定人口
データ無し
推定人口の順位
不明
※本サイトではプライバシー保護のため人口が少ない場合は[0~10前後]、[ほとんどいない]等と表現し、端数についてはも四捨五入させているため[全国の推定人口]と各都道府県の[人口]の合計は一致しません。
安姓 ランキング上位
 茨城県(約2,300人)
茨城県(約2,300人)
 東京都(約670人)
東京都(約670人)
 神奈川県(約220人)
神奈川県(約220人)
 千葉県(約210人)
千葉県(約210人)
 埼玉県(約150人)
埼玉県(約150人)
安姓 県内比率ランキング上位
 茨城県(約0人)
茨城県(約0人)
 鹿児島県(約0人)
鹿児島県(約0人)
 東京都(約0人)
東京都(約0人)
 千葉県(約0人)
千葉県(約0人)
 福島県(約0人)
福島県(約0人)
安姓都道府県分布一覧
| 都道府県 | 人口 | 県内比率 |
|---|---|---|
| 0~10前後 | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| 約40 | 0.00% | |
| 約2300 | 0.08% | |
| 約50 | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| 約150 | 0.00% | |
| 約210 | 0.00% |
| 都道府県 | 人口 | 県内比率 |
|---|---|---|
| 約670 | 0.00% | |
| 約220 | 0.00% | |
| 約20 | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| 約50 | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% |
| 都道府県 | 人口 | 県内比率 |
|---|---|---|
| 約20 | 0.00% | |
| 約20 | 0.00% | |
| 約140 | 0.00% | |
| 約70 | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% |
| 都道府県 | 人口 | 県内比率 |
|---|---|---|
| ほとんどいない | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| 0~10前後 | 0.00% | |
| ほとんどいない | 0.00% | |
| 約100 | 0.01% | |
| 0~10前後 | 0.00% |
安姓の地域分布
安姓の都道府県分布
安という名字は全国で3212番目に多い苗字となっています。約10万人に3人そこそこ居る可能性があります。茨城県や東京都や神奈川県や千葉県や埼玉県や大阪府によくいらっしゃるようです。また県内の人口比率だと茨城県や鹿児島県や東京都や千葉県や福島県や栃木県にいらっしゃるようです。地域としては関東地方に多い名前のようです。もしかすると地名に安さんの苗字のが使われていたりするかもしれません。調べてみると意外なことがわかるかもしれませんね。ひょっとすると安という苗字の高名な方がいらっしゃったのかもしれません。そして茨城県や鹿児島県や兵庫県に移り住まわれた方が多いようです。その後全国に広がっていったと思われます。
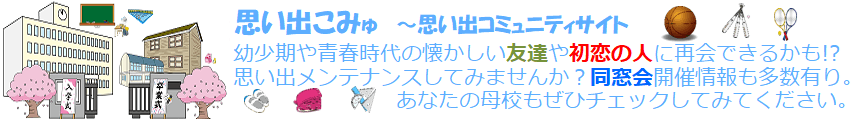
安さんの由来
- 安国造、安郡公、安宿禰、中臣鎌足が天智天皇より賜ったことに始まる氏(藤原氏)。藤原南家乙麿流などにもみられる。また東亜細亜(中国)姓、韓国・朝鮮姓にもみられる。 鎌足─不比等─〔南家祖〕武智麿─〔南家乙麿流〕乙麿─是公─雄友─弟河─高扶─清夏─維幾─〔南家為憲流〕為憲……正義……〔安氏の祖〕安鎌人之佐藤原正忠。 藤原鎌足10世の藤原維幾(従五位上武蔵守・常陸介)を祖とし、その15世正義は鎌倉の関東公方足利氏満に仕ヘ、武州橘樹郡飯野郷朝日平沢2村を給い、その九世の正忠は武田民部少輔信是(信虎五男・信玄の弟・松尾城主)に仕ヘ下野国足利郡安野安応安鷲3村に於いて永五十貫を給いその偏字を取リ氏を安と改めた。1590年秀吉が全国統一。徳川家康は秀吉の命令で、駿河国・遠江国・三河国・甲斐国・信濃国の5ヶ国を召し上げられ、北条氏の旧領、武蔵国・伊豆国・相模国・上野国・上総国・下総国・下野国の一部・常陸国の一部の関八州に移封された。武田(松尾)信是(~1571)の没後は信玄の命により、弟・河窪信実(かわくぼ のぶざね)の息子河窪信俊が家督を相続。天正10年(1582年)の武田家滅亡後は徳川家康に仕え、子孫は旗本(2700石)となっている。その子信貞の代に松尾姓から武田姓に復している。 武田信玄に大いに苦しめられた家康ではあるが、施政には軍事・政治共に武田家を手本にしたものが多い。天正10年(1582年)の武田氏滅亡・本能寺の変後の天正壬午の乱を経て武田遺領を確保すると、武田遺臣の多くを家臣団に組み込んでいる。慶長7年(1602年)自分の五男・信吉に「武田」の苗字を与え、武田信吉と名乗らせ、常陸国水戸25万石に旧穴山家臣を中心とする武田遺臣を付けられて武田氏を再興し水戸藩を治めさせている。 慶長8年(1603年)9月11日、信吉は生来病弱であったらしく、わずか21歳で死去し武田氏は再び断絶した。水戸藩は異母弟の頼将が入り、頼将が駿府に移封の後は、同じく異母弟の頼房が入部し、水戸徳川家の祖となる。信吉の家臣の多くは水戸家に仕える。 それに伴い藤原(安)正忠も常陸国(現茨城県ひたちなか市)に移る。藤原維幾は桓武平氏の平高望(従五位下上総介)の娘を妻としその子為憲は工藤氏の祖となる。安は藤原氏であるとともに桓武平氏の子孫でもある。
- 安の系譜(中臣⇒藤原⇒工藤⇒安) •飛鳥時代 - [592年 ~ 710年] 初代・中臣鎌足=大化の改新、天智天皇から大織冠位と藤原姓を賜わる 2代・藤原不比等=従一位・左大臣、式部卿・大宰帥、奈良時代初期公卿 3代・藤原武智麿=正二位・左大臣、贈太政大臣、奈良時代前期の貴族。 •奈良時代 - [710年 ~ 794年] 4代・藤原乙麿(おとまろ)=従三位・武部卿、奈良時代の公卿 5代・藤原是公(これきみ)=従一位・右大臣、奈良時代後期の公卿 •平安時代 - [794年 ~ 1185年] 6代・藤原雄友(おとも)=正三位・大納言、平安時代初期の公卿 7代・藤原弟河(おとかわ)=従五位下・越前介、伊賀守、平安時代初期の貴族 8代・藤原高扶(たかすけ)=従五位上・陸奥守、平安時代初期の貴族 9代・藤原清夏(きよなつ)=上総介、左少弁 10代・藤原維幾 939 天慶2年 従五位上・武蔵守、常陸介【常陸府中(石岡) 】、讃岐介 11代・工藤爲憲 従五位下・遠江権守。工藤大夫を号す •鎌倉時代 - [1185年 ~ 1333年] 伊豆工藤 奥洲工藤 12代・工藤時理─時信─維永─維景─景任─行景─景隆─景光─重光─高光─ ┗※今上(平成)天皇の直系祖先 得宗被官工藤氏(重光流) 22代・工藤時光 得宗家公文所執事、若狭国(得宗分国)守護代。 •室町時代 - [1336年 ~ 1573年] 23代・工藤貞祐 若狭国【得宗(鎌倉幕府北条氏)分国】守護代、摂津国多田院造営惣奉行。 24代・工藤高景 鎌倉幕府の北条氏・大和道軍軍奉行 25代・藤原正義=同族二階堂氏と共に室町幕府の関東府(鎌倉) 足利氏満の御家人 •安土桃山時代 - [1573年 ~ 1603年] 33代・(安)藤
【名字由来教えてください】
安姓の由来やルーツ、一族の伝承や秘話等についてご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
他の苗字の全国の分布を調べる
同じ名字の人と交流する
同じ名字の人が集うページを設置しております。同姓の方と交流してみてください。安姓についてもっと詳しく
© 2013-.
sijisuru.com All rights reserved.
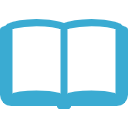 安姓のページ
安姓のページ 安の由来
安の由来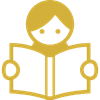 安の読み方
安の読み方 安姓の人口
安姓の人口 安姓の特徴
安姓の特徴 安姓のイメージ
安姓のイメージ 安姓交流掲示板
安姓交流掲示板 相性のいい女子の名前
相性のいい女子の名前 相性のいい男子の名前
相性のいい男子の名前 安姓の有名人
安姓の有名人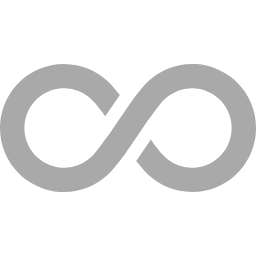 ダジャレを作る
ダジャレを作る