掲示板トップ > 三田地姓の掲示板
投稿
|
今回サイトで初めて知りましたが、岩手の名産『南部せんべい』にも長慶天皇伝説がありました。天皇が南部地方巡幸のおり南部せんべいを供したという内容ですが、明治天皇や昭和天皇も東北を巡幸しており時代の混濁があるのではないかと思ったりもします。長慶天皇伝説の多い北奥は険しい山が多く平地が少ないため米作は発展しにくい土地柄です。大麦やそば粉が原料で胡麻をまぶした素朴な風味が人気の南部せんべいですが、よく見ると菊水の紋様がせんべいに描かれていて伝説を裏づけていると思われます。また、南部藩兵の野戦食であったとも云われています。江戸時代末期になると奥羽の諸藩はロシア防衛のため幕府の命で要所に陣屋を構築するなど北海道(蝦夷地)警備を実施しています。 (2024/01/14 11:41:00:三浦屋) 南朝の長慶天皇は実は、長い間実在しなかった天皇であると言われ続けてきましたが、大正年間になってようやく皇統譜に列せられました。京都市右京区嵯峨天竜寺の嵯峨東陵に葬られている事が判明し宮内庁もこれを認めたという経緯があります。長慶天皇は運悪く南朝衰退時に生まれ行宮も転々とされて四国にまでその遺蹟を残します。東北においては、即位前に陸奥太守に任命された伝承があって八戸の櫛引八幡宮には長慶天皇が着用されたという豪華な鎧兜が宝物殿に残されております。また、浪岡町の天狗平山には御陵墓比定遺構が現存しています。大正年間以降に嵯峨東陵が天皇の御墓所であると決定されている今、天狗平山に葬られている貴人はいずこの方か大いに気になる処であります。長慶天皇はあの後醍醐天皇の孫にあたる方であり浪岡御所の祖先は南朝の重鎮(後醍醐天皇の信任厚かった)北畠親房につながる名門の血統です。考えられることは北畠氏の誰かか十三湊安東氏やその前の藤原氏(平泉の系統)ですがこれは単なる私見に過ぎません。浪岡一帯の治安が安定していた頃は安東氏の時代でした。そして安東氏の勢力が衰え領主が南部氏に交替しました。南部氏も長らく伊達や結城と共に南朝の中心勢力でありましたが、北朝に寝返った時もあります。さらに南北朝統一の時代となり北畠氏を此処に置くのはまずいということで、岩泉の袰綿に転居させたのではないかと云われています。 (2024/01/08 14:00:00:三浦屋) 秋田県大館市の北方に白神山系田代岳があります。この付近に長慶金山(長慶森H=942m)という金山がかつてありました。金山の規模など具体的なことはよく判っていませんが、南朝の長慶天皇が隠居したあとに開山した伝えがあり上皇堂の地名を残しています。金山伝説としては有名な箇所です。このあたりは南北朝の昔から浪岡御所や原常館、天狗平山の御陵墓比定地などがあり長慶天皇伝説は数多く存在します。 (2024/01/08 10:43:00:三浦屋) 南部藩領では県北の白銀金山や尾去沢金山が大規模で有名でしたが、金を取り尽くした後は銅山採掘に変わっています。ただ金堀工は銀や銅、砂鉄を採掘しながら或いは砂金を採取しながらピンポイントで脈の有りそうな山々を調べ歩いていたに違いありません。鼠入山金山もそのひとつであったと想像されます。府金三田地家は古くから沢廻地区(清水川流域)の肝入であり藩から鉱山、鍛冶管理を任されていた家であると考えるのが妥当であろうと思います。鼠入川三田地家はこの分かれのような気がします。鼠入山の金山に携わった家ということになります。 (2024/01/04 18:04:00:三浦屋) 岩手県史の鉱山の項に、江戸時代の享保14年(1729)鼠入山金山とみえます。野田通り岩泉代官管内のことです。南部藩では『通り』の名称で藩内を分けていました。鼠入山の具体的な位置はよくわかりませんが、鼠入川に関係した山かと思われます。関ヶ原の戦いが1600年ですから享保年間は100年以上経過しております。 (2024/01/04 14:24:00:三浦屋) 2024年辰年明けておりますが、今年は初っぱなから地震、津波ときょうになって航空機事故と大災害続きです。亡くなられた方々にお悔やみを申し上げる共に、被災者の皆様には一時も早く日常の生活に戻れるよう祈念しております。東日本大震災で被災したときの事が思い出されますが、東北地方の太平洋側におきましても、未まだに千島海溝、日本海溝と巨大地震の巣を3〜4つ抱えており状況はひっ迫しております。ですが、私共はまず生き延びる事を考えねばなりません。 (2024/01/02 22:33:00:三浦屋) 鼠入川に住む三田地家の記事は以前にも何度か書いたことがあります。たしか当主が議員さんの経験を持つ家でした。三田地一族にまつわる御刀伝説の事も知っており、自説ではこの家は三十三代続いているとも主張されていました。ご存知のように北上山系は日本有数の砂鉄産地です。南部藩は江戸時代の天保年間で鉱山を124箇所保有していましたが、岩泉や宮古のある閉伊郡は断トツで54の鉱山が稼働していました。藩政当初に閉伊郡の中枢を担った岩泉南部氏のゴタゴタが続いたせいでしょうか、そんな中で数少ない金山の記録もあります。 (2023/12/30 19:28:00:三浦屋) 下新屋を含め岩泉三田地姓は清水川しづがわ流域に多く見られます。清水川西側の山一帯が昔から字府金ふがねの地名になっており肝入の三田地家が居を定めていた所です。長い間に多くの分家や別家がうまれてこの一帯に同族が住むようになったようです。岩泉地方だけでなく他の村々にもよく見られる形態です。このなかでちょっと距離があって流域もちがう鼠入川そいりがわ地区にも三田地の旧家があります。直系血族100人を超える家(東北では通称マキと言っています)として昭和40年代にTVで紹介されました。なぜこの離れた地区に同族でもある三田地家が居を構えているのか謎です。 (2023/12/29 10:23:00:三浦屋) あらや、にいや(新屋、新谷、荒谷)は全国どこにでもある地名です。荒れ地だったところを新田開発して新屋にいや(独立して新しく建てた家すなわち分家、別家など)に住むことになった由緒を物語っているそうです。ただ、そのような経緯もあったかも知れませんが、なかにはアラハバキの[荒あら]を指している場合もありそうです。岩泉町にも下新屋しもにいや、中新屋なかにいや、上新屋かみにいやの屋号をもつ旧家があり、新にいは荒あらだった可能性もあるわけです。三田地家にも下新屋の屋号を名乗る家があります。ここで説明しておきますが、アラハバキと三田地家が関係あるのだと云うことを言っているわけではありません。 (2023/12/23 14:33:00:三浦屋) 億ウソ流ではアラハバキ系の苗字や地名が今なお残っていると主張しています。たとえば、荒井、荒あら、荒田、荒屋敷などなどになります。変形タイプでは、安良城あらき、新(仁)井田、あらいだへ、にいだ、洗川あらかわ、新井あらい等々があります。 (2023/12/17 16:35:00:三浦屋) |
三田地さんの掲示板
全国の三田地さんに関する掲示板です。三田地さんに関するエピソードや三田地さんの由来、「三田地会」、「三田地」サークルなどの存在や三田地さん限定サービスなどのお得情報等、三田地さんに関することを教えてください。足跡&一言だけでもぜひお願いします!!
このページは自分のお仕事をPRしたり、ホームページのアドレスを載せてもOKです。 ただし無関係の広告や自分の名前ではないページでのPRは削除します。
※個人を特定できる投稿はしないでください。
この掲示板は 18406名の人に閲覧されています。
三田地姓についてもっと詳しく
© 2013-.
sijisuru.com All rights reserved.
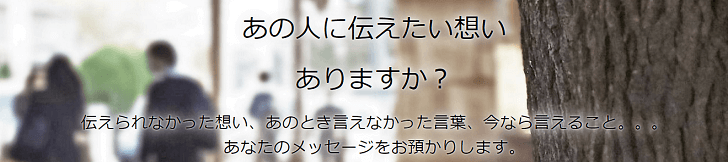
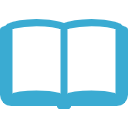 三田地姓のページ
三田地姓のページ 三田地の由来
三田地の由来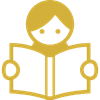 三田地の読み方
三田地の読み方 三田地姓の人口
三田地姓の人口 三田地姓の特徴
三田地姓の特徴 三田地姓のイメージ
三田地姓のイメージ 相性のいい女子の名前
相性のいい女子の名前 相性のいい男子の名前
相性のいい男子の名前 三田地姓の有名人
三田地姓の有名人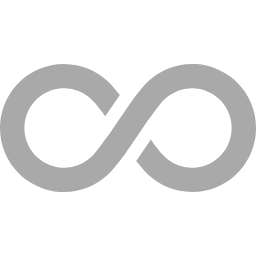 ダジャレを作る
ダジャレを作る