掲示板トップ > 三田地姓の掲示板
投稿
|
あらや、にいや(新屋、新谷、荒谷)は全国どこにでもある地名です。荒れ地だったところを新田開発して新屋にいや(独立して新しく建てた家すなわち分家、別家など)に住むことになった由緒を物語っているそうです。ただ、そのような経緯もあったかも知れませんが、なかにはアラハバキの[荒あら]を指している場合もありそうです。岩泉町にも下新屋しもにいや、中新屋なかにいや、上新屋かみにいやの屋号をもつ旧家があり、新にいは荒あらだった可能性もあるわけです。三田地家にも下新屋の屋号を名乗る家があります。ここで説明しておきますが、アラハバキと三田地家が関係あるのだと云うことを言っているわけではありません。 (2023/12/23 14:33:00:三浦屋) 億ウソ流ではアラハバキ系の苗字や地名が今なお残っていると主張しています。たとえば、荒井、荒あら、荒田、荒屋敷などなどになります。変形タイプでは、安良城あらき、新(仁)井田、あらいだへ、にいだ、洗川あらかわ、新井あらい等々があります。 (2023/12/17 16:35:00:三浦屋) アラハバキの言葉がいつ頃からあったのかよく分かりませんが、例えば仙台市青葉区に今も荒巻の地名があります。今でこそ大字相当の地名になっていますが、かつては仙台地方全体の地名であったとされアラハバキが変化した地名と言われます。源頼朝が平泉藤原氏を征討した後、鎌倉御家人を奥州へ下向させ論功行賞の所領を各家で治めるようになりました。この頃仙台平野は国分氏(千葉氏)が治めるようになって国分庄と呼ばれるようになり本家本流の留守を預かる意味で一族は留守氏とも名乗りました。国分庄になる前、仙台地方は荒巻、荒牧と呼ばれていた可能性があると考えます。 (2023/12/17 09:43:00:三浦屋) 特に三内丸山縄文遺跡の発掘以来、様々な面で縄文期のイメージはだいぶ変化したわけであります。縄文人たちの行動は想像以上に範囲が広く、列島内に関わらず大陸との交易もあって半島に移住した縄文人グループも居ました。長期間にわたる交易活動は海路陸路の輸送に伴い地名や言葉或いは産物の名称などをも発達させたと想像されます。 (2023/12/17 09:11:00:三浦屋) 青森県には、三内丸山のほか縄文遺跡が数多くありますが、陸奥湾の海岸沿いの砂丘から縄文期の墓、十数基が発見されたことがありました。墓の形態は直径3メートルくらいのマウントです。いわゆる土饅頭です。土饅頭のてっぺんに石柱が建てられていたそうです。県教委では始め特別な身分の人たちの墓群であろうとの見解でしたが、精査を重ねた結果一般庶民の墓群である事がわかりました。約3000年前くらいの遺跡だったでしょうか。長い間の強烈な海風で墓群は砂の下になってしまい忘れ去られてしまったものと考えられます。 (2023/12/10 16:10:00:三浦屋) 億ウソ流の主張であるハルハキ➡️アラハバキへの変化も大いにあり得ると考えます。ならば、吉林や魏の前の時代はアラハバキ以外の名称だったのだろうか。アラハバキ神の起源は一般には縄文であるとされていますが、モンゴロイド集団が日本に移住して来たのは数万年前の事になるので歴史的には縄文の起源どころではありません。あまりに古い事象はよく解からないままアラハバキ神の起源を縄文としたものか不明です。 (2023/12/09 17:06:00:三浦屋) 北アジアの河川で歴史上思い出す川にハルハ川があります。旧満州とモンゴルの国境を流れる川であり1939年に勃発したノモンハン事件の舞台となった川です。年間の平均流量からすると宮城の鳴瀬川くらいの規模の川です。旧ソ連邦ではハルハ河会戦といい圧倒的火力の前に日本陸軍は大負けしたおり実際の被害は甚大なものでした。モンゴル語をハルハ.モンゴル語というくらい蒙古では昔から重要で大切なハルハ川です。このハルハに吉(吉林省の吉林を指す)あるいは魏(三国志の曹操の時代)を併せた合体語をハルハキと言い、これが長い間に変化してアラハバキと発音するようになったというのが億ウソ流です。 (2023/12/08 22:07:00:三浦屋) 中国が隋や唐の時代、沿海州に靺鞨国があって多賀城から三千里の距離があると壺の碑(日本の三古碑の一つとされ多賀城南門近くに建つ)に刻まれています。靺鞨は沿海州に居たツングース系族からなっており昔は農耕漁労を生業としていました。多賀城時代にはすでに律令政府と交流があったとされ、その子孫は金や清を建国した満人につながる系統です。沿海州とは近代はロシア領、州都はウラジオストックです。アムール川の支流であるウスリー川東側一帯(日本海側沿岸)を指します。 (2023/12/03 22:47:00:三浦屋) アラハバキの故事来歴については前にも述べたので割愛しますが、関東や関西、九州にもアラハバキ神社は存在します。これはアラハバキ神が元からその地方に祀られていたと解され日本人の源流、祖霊神に関わるレベルかと思います。一説には縄文人の祀った神とも云われています。東北の寒冷地化から縄文人グループが南下していった痕跡も所々に見受けられる(青森の三内丸山消滅など)ので可能性としてはゼロでは無いと考えられます。多賀城のアラハバキ小社が西を向いている意味は大陸の母(オボ)なる川であるアムール川信仰の影響だろうかなどと想像したりします。すなわち縄文人の祖先は遥か蒙古、バイカル湖周辺で暮らしていたとする説と合致します。 (2023/12/02 23:02:00:三浦屋) 神社や祠はほとんどが南向き、東向きに建っているものですが、このアラハバキ小社は城外の西向きにひっそりと建っています。強いて言えば多賀城東門か政庁の方を向いています。720年頃に郡山官衙から国府を多賀城に引っ越したのは初期の目的を予定通り達成させた為と察せられ、大地震や津波で被災した痕跡は官衙跡にはありません。多賀城の立地は海岸に近い高台であり資源物資の集積輸送が増えてきた事への対策や三陸方面への展開(海道の蝦夷の存在あり)を考えたのかも知れません。初めに郡山に官衙を置いたのは陸奥国建国と併せて出羽国建国の目標設定があったのだと考えられます。陸奥大道から笹谷峠への分岐点が古代から郡山付近にあったと想像されます。 (2023/12/02 15:26:00:三浦屋) |
三田地さんの掲示板
全国の三田地さんに関する掲示板です。三田地さんに関するエピソードや三田地さんの由来、「三田地会」、「三田地」サークルなどの存在や三田地さん限定サービスなどのお得情報等、三田地さんに関することを教えてください。足跡&一言だけでもぜひお願いします!!
このページは自分のお仕事をPRしたり、ホームページのアドレスを載せてもOKです。 ただし無関係の広告や自分の名前ではないページでのPRは削除します。
※個人を特定できる投稿はしないでください。
この掲示板は 18426名の人に閲覧されています。
三田地姓についてもっと詳しく
© 2013-.
sijisuru.com All rights reserved.
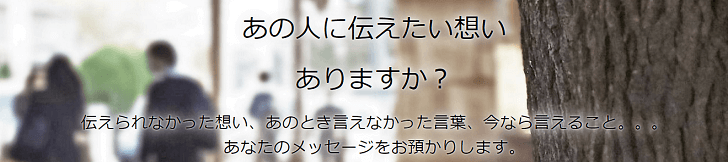
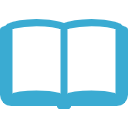 三田地姓のページ
三田地姓のページ 三田地の由来
三田地の由来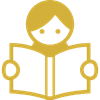 三田地の読み方
三田地の読み方 三田地姓の人口
三田地姓の人口 三田地姓の特徴
三田地姓の特徴 三田地姓のイメージ
三田地姓のイメージ 相性のいい女子の名前
相性のいい女子の名前 相性のいい男子の名前
相性のいい男子の名前 三田地姓の有名人
三田地姓の有名人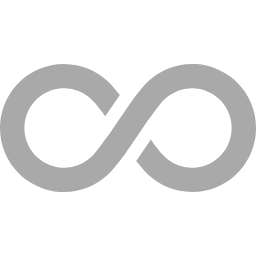 ダジャレを作る
ダジャレを作る